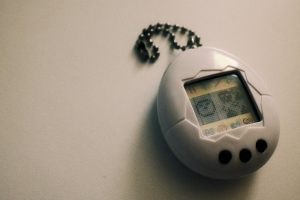靖国神社境内に併設された「遊就館(ゆうしゅうかん)」ですが一部でやばいとの声が上がっているようです。
今回はそんな声を調査しました。
遊就館がやばいとの声:圧巻の展示品

靖国神社境内にある遊就館は、22の展示室を有する博物館・宝物館であり、英霊の遺書や遺品の展示、ゼロ戦の戦闘機や艦上爆発機「彗星」などの軍機が展示され、日本国内外の戦乱・戦争について学ぶことが出来る資料が盛りだくさんとなっています。
そんな遊就館ですが、ネット上には「やばい」口コミが多く寄せられています。
数ある口コミの中で、特に多かったのが「展示品」に関する口コミです。
遊就館の展示品に関する口コミは以下の通りです。
このように、実際に遊就館に行った人からは「展示品」に関する口コミが多く寄せられていて、多くの人が展示品に感動していることが分かりました。
遊就館には、戦争で亡くなられた方の遺書や遺品、さらには戦闘機などといった戦争に関する展示がされているため、リアルな展示品に「胸が熱くなった」という声も少なくありません。
初めて遊就館に行った人は時間が足りないと感じ、気軽に立ち寄るだけではもったいないという意見が目立ったため、しっかりと時間を確保したうえで遊就館に行くことをおすすめします。
遊就館がやばいとの声2:大人から子ども楽しめる
遊就館は、靖国神社に鎮まる英霊の遺書や遺品をはじめ、貴重な史・資料、絵画や美術品、武具甲胄、武器類など約10万点の収蔵品を展示していて、時間に余裕をもっていく必要があります。
ゆったりとした雰囲気のため子ども連れには厳しいのかと思いきや、実は館内も広く、展示品も子どもにも興味を持ってもらえるものとなっていて、大人から子どもまで幅広い世代で楽しむことが出来ると言われているのです。
子ども連れとなるとどうしても館内の広さが気になりますが、遊就館は22の展示室があるためかなり広い造りとなっています。
また、館内4か所には女性用トイレと多目的トイレの他にオムツ交換機があり、隣接する靖国会館1階の無料休憩所は飲食の持ち込みが可能なので、小さな子どもを連れていても安心して楽しむことが出来ます。
遊就館は戦争博物館のような施設でもあるため、子どもには何をどう伝えるのか、子どもが教科書で読むことと学校で出される宿題の内容に相違が無いようにと考えさせられたという声もあり、子どもの学習に良いだけでなく、親にとっても勉強となり学ぶことが多い施設であることが分かりました。
遊就館の見どころとは
遊就館には零戦をはじめ多くの見どころがあります。
①1階の零戦や戦車
遊就館の1階には零戦や戦車、機関車などが展示されていて、零戦は五十二型と言われる三菱重工業で造られたモデルであり、エンジンは1140馬力、最高速度は550キロと言われ、零戦ファンにはたまらない魅力があります。
さらに1階の展示室には零戦以外にも戦車や機関車などが展示されている他に、細かい細工が施された軍艦の模型があるので、当時の雰囲気に浸ることが出来るのです。
零戦の正式名称は「三菱零式艦上戦闘機五二型」と言われ、操縦席が狭く、機体自体もコンパクトに造られています。
1階に展示されている零戦は、戦地で残骸となった零戦数機の機体を拾い集めて復元されたものなのです。
②2階の有料展示
2階には明治維新や戊辰戦争から始まる日本の歴史の資料が時系列的に展示されていて、その他にも刀剣類や古代銃、戊辰戦争で官軍が掲げていた綿の御旗や零戦の模型などの展示があります。
また、皇室ゆかりの品や、特別展示室には天皇の肖像画や旭日旗、陸軍軍旗や菊家紋の竿頭など、普段はなかなか見ることが出来ない展示品が多く展示されているのです。
見どころの多い2階は有料エリアとなっており、一般が1000円、大学生が500円、中高生が300円、小学生以下が無料となっていて、靖国神社を正式参拝することで遊就館の招待券を貰うことが出来るので、ぜひ2階の有料展示も見ることをおすすめします。
遊就館についておさらい
遊就館とは、明治10年の西南戦争が終わるころの設立の構想が出され、明治12年に陸軍卿・山県有明を中心に、「御祭神の遺徳を尊び、また古来の武具などを展示する施設」として構想され、イタリアの雇教師カペレッティーの設計により、明治14年にイタリア古城式の建物が竣工し、翌年の15年2月25日に開館式が行われました。
館名については、構想段階で正式名称が決定するまでは「額堂並に武器陳列場」と仮称されていたのですが、後の宮内臣田中光顕伯爵が学者吉雄菊瀕の原案に基づいて正式名称を「遊就館」と決定したのでした。
遊就館に関するQ&A
- 遊就館の名前の由来は何ですか?意外と知られていない深い意味があるそうですが。
遊就館(ゆうしゅうかん)という名称は、中国の古典である『荀子・勧学篇』の一節、「君子は居るに必ず郷を擇び、遊ぶに必ず士に就く」に由来します。
「君子は住むのに必ずふさわしい土地を選び、交わるには必ず徳の高い人物に就く。そうすることで、よこしまな道を避け、中正に近づくことができる」という意味です。
「遊必就士(遊ぶに必ず士に就く)」の部分から「遊就館」と名付けられました。
靖国神社に祀られている祭神(英霊)の崇高な徳に触れ、その行いを学ぶことで、正しい道を歩むべきだという設立の理念を示しています。
単に軍事資料を展示するだけでなく、祭神の「みこころ」を後世に伝え、慰霊と顕彰の念を育むことを目的とした施設であることが、その名前に込められています。
- 遊就館はいつからあるのですか?
遊就館は1882年(明治15年)に開館した、日本で最初かつ最古の軍事博物館です。
西南戦争後、陸軍卿であった山縣有朋を中心に、戦没者の遺徳を尊び、古来の武具などを展示する施設として構想されました。
しかし、その歴史は平坦ではありませんでした。
- 関東大震災による倒壊
1923年(大正12年)の関東大震災でレンガ造りの建物が大破し、撤去されました。 - 再建と再開
建築家の伊東忠太を顧問に迎え、近代東洋式(帝冠様式)の現在の本館が建設され、1932年(昭和7年)に再開館しました。 - 戦後の休館
第二次世界大戦の敗戦により1945年9月に閉館。その後、建物は空襲で社屋を失った富国生命保険相互会社に本社事務所として1980年(昭和55年)まで貸し出されていました。 - 再開館と改装
1986年(昭和61年)に約40年ぶりに再開。その後、靖国神社御創立130年を記念し、2002年(平成14年)に本館を全面改装し、新館を増設して現在の姿になりました。
- 関東大震災による倒壊
- 遊就館の展示は、どのような視点で構成されているのですか?「靖国史観」という言葉も聞きますが。
遊就館の展示は、靖国神社に祀られている祭神(英霊)の遺品や遺書を通じてその事績を伝え、見学者に慰霊と顕彰の念を育んでもらうことを主目的としています。その歴史叙述は、しばしば「靖国史観」と評されます。
この視点の主な特徴は以下の通りです。
- 大東亜戦争の肯定
満州事変から大東亜戦争に至る一連の戦争を、欧米列強の植民地支配からアジアを解放し、日本の自存自衛を守るための正当な戦いであったと位置づけています。 - 「英霊」の顕彰
戦没者を国家のために尊い命を捧げた「英霊」として一貫して描き、その自己犠牲の精神を称揚します。 - 日本の「被害」の強調
アメリカによる対日経済封鎖(ABCD包囲網)などが開戦の要因であったと強調し、日本が戦争に追い込まれたとする側面を強く打ち出しています。
- 大東亜戦争の肯定